トレーニング初心者やこれから始める人は、この原理原則を知っておくことでトレーニングの効果を体感することができます。逆に言えば、これらを知らないでやると効果が得られにくかったりするので注意してください。
- 過負荷の原理
- 特異性の原理
- 可逆性の原理
・全面性の原則
・意識性の原則
・漸進性の原則
・個別性の原則
・反復性の原則
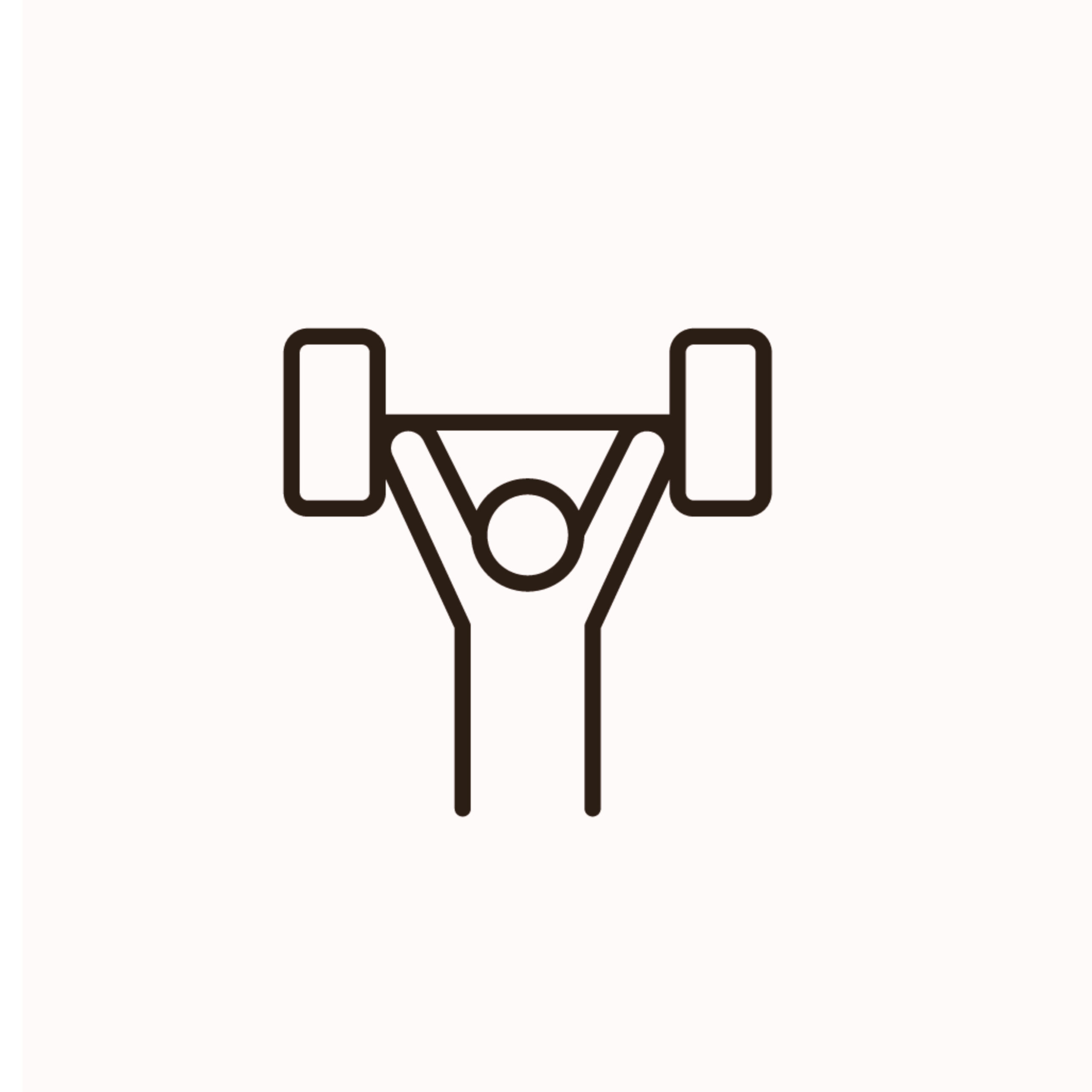
しっかり結果を出したい人ほど要チェックです!
過負荷の原理
少しづつ負荷を高めていくことで、筋力や体力は向上するという原理。
同じ負荷では身体は慣れてしまうので停滞に繋がることもあります。
例えば、現在スクワット50キロ8回×3セット ができるなら→スクワット55キロ8回×3セット、50キロ10回×3セット
のようにできる範囲で負荷やセット数などを増やしていくように、
通常のトレーニングでは回数や重さが伸びていくことはトレーニング始めたてから数年は実感しやすいです。
重さがすべてではないですが、もしマンネリ化しているのなら過負荷ができているか確認してみてください。
特異性の原理
トレーニングによって与えたその刺激に対して、身体は適応するという原理。
例えば、脚の筋肉を大きくさせるために本来スクワット10回×3セットで限界までやる。というプログラムが適しているのにも関わらず、ジョギングを30分間する。という間違った方向にプログラムを組んでしまう場合。
トレーニングを通して身体にどんな変化を起こさせたいのか?こちらも確認してみましょう。
可逆性の原理
トレーニングしない期間が続くと、身体は元に戻っていくという原理。
三週間以上空くと筋力の低下などがみられるようです。これは今までのトレーニング歴やレベルによってもどれくらい戻るのかは変わってくるのですが、期間を空けすぎないように注意したいところです。
トレーニング歴が長い人のほうが、短い人に比べてトレーニングしていない期間が空いてしまっても筋力の戻りが早いことが知られています。


全面性の原則
全身のトレーニング及び必要となる体力要素を満遍なく実施しましょうという原則。
腕のトレーニングが好きでそれだけ実施するのではなく、ストレッチ含め胸や背中など満遍なくトレーニングした方が発達も見込めますし、ケガの予防にもつながります。
よほどのこだわりがない限りは全身バランスよく鍛えましょう。
意識性の原則
トレーニングの際に、どこの筋肉を使用しているか意識することで効果が高まるという原則。
効いている感覚を意識することもですが、やっているトレーニングの目的や効果を合わせて理解することが大切です。
漸進性の原則
少しずつトレーニングの強度を筋力・体力レベルに応じて変化させていきましょうという原則。
重さ・回数・セット数・インターバル・頻度・順番・バリエーションなど多くの変数から選択し徐々に負荷を高めていく必要があります。
停滞している人は現在のトレーニングを見直すべき一番のポイントといえそうです。
個別性の原則
トレーニングは体力・年齢・身体・癖・生活習慣などそれぞれに合わせてしましょうという原則。
SNSで見かけるようなトレーニングを例に挙げれば、それは果たして自分に合っているのか「どうか再考する必要があります。同じことをしても結果が出る出ないあもちろんあります。
自分に合ったトレーニングとはなんなのか。パーソナルトレーナーにアドバイスをもらうのも一つです。
反復性の原則
トレーニングは反復して行うことで一定の効果が得られるという原則。
まさに継続は力なりです。たとえ一か月以上空いてしまっても年間を通してプログラムがなされていたりすれば問題はないかと思います。
トレーニング初心者の方は難しく考えずに一か月に2回できたらいいなぐらいにハードルを低めに設定してあげる方が継続しやすいと思います。毎日やる必要があるのか、といわれればノーです。


まとめ
いくらハードに毎日トレーニングをしていても、これらの原理原則を無視してトレーニングすることは効率が悪いです。
今しているトレーニングを見直すきっかけになれば幸いです。
漸進性の原則と反復性の原則の2つは特に大切と思います。

