本記事では、登山をしている方これからする方で「疲れやすい」「もっと体力をつけたい」「登山向けトレーニングをしたい」といった悩みをお持ちの皆さまに向けて書いております。
ではそれらの悩みを解決するための下半身のトレーニングを3つご紹介していきます。
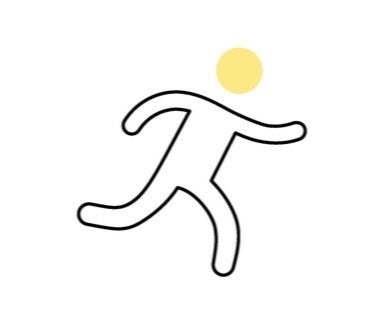
体力・筋力がつけばまだ登ったことのない山にも登れます
登山向けトレーニングについて
登山は有酸素運動なので、ランニングやバイクがいいのではないか、もちろんそれらも大切なのですが筋トレをすることで皆さまのパフォーマンスは確実に高まります。疲れにくい身体を手に入れましょう。
トレーニングがなぜ効果的かというと、身体のキャパを増やし効率の良い力発揮の仕方を獲得できるから という理由が挙げられます。


100㎞/hしか出せない車と200㎞/h出せる車で、常に80㎞/hで走るとき燃費がいいのはどちらかということ。もちろん200㎞/h出せたほうがいいんです。
有酸素運動や食事、筋トレにはこのキャパを広げて燃費のいい身体を作ることが可能なのです。
登山での身体の使い方
登り
前半緩やかな坂道を登っていく局面では、歩行のフェーズが多いため関わる要素は姿勢保持能力や歩行の効率性が求められます。体幹部や股関節周囲の筋群が適切に機能していない場合には、姿勢や歩行が乱れ筋肉や関節に負担がかかってきます。次に険しい坂道や崖、階段を登るときです。よりたくさんのエネルギーを短時間で使う局面であるといえます。心肺機能と筋力・筋持久力・パワー・身体の使い方がより求められます。
筋トレでここを強化したらより疲れにくい身体になること間違いなし!
下り
登りがアクセルなら下りはブレーキしながら身体を使います。自分の体重+重力を傾斜がある状態で受け止めなければいけないので下りも想像以上にエネルギーを使います。
全体を通していかに効率よく少ないエネルギーで登れるかが大切です。


登山のパフォーマンスを上げる要因
では、登山のパフォーマンスを上げるためには何が必要なのでしょうか。
姿勢・歩行・心肺機能・筋持久力・筋力・パワー・平衡性・柔軟性・協応性・(敏捷性・スピード)・メンタル・栄養・視機能・前庭機能など
このように様々な要素が複合的に作用し合うことでパフォーマンスが決まってきます。この中で、誰でもできて土台を伸ばしやすいのが、心肺機能・筋持久力・筋力 といった要素になります。ジムでのトレーニングを積めば目に見えて効果もわかりやすく登山のパフォーマンスへの影響も大きいでしょう。
ジムでできる下半身のトレーニング3選
ルーマニアンデッドリフト
1.足は腰幅、手は肩幅
2.お尻の位置を変えずに上半身をまっすぐ折り曲げる(膝は軽く曲がる)
3.もも裏にテンションがかかる感覚を得て元の位置に戻る
※バーベルが身体から離れていかないように
鍛えられる筋肉:ハムストリングス(もも裏)、大殿筋など
推奨ボリューム:8~12回 2~3セット
スクワット
1.足は肩幅、つま先やや外
2.くるぶしから踵のあたりに体重がかかりそのまま真下にしゃがみます
3.前後に重心移動しないようにお尻が膝と同じ位置まできたら立ち上がりましょう
※バーベルの軌道を確認して下さい。
鍛えられる筋肉:大殿筋、大腿四頭筋、内転筋、など
推奨ボリューム:5~10回 2~3セット
リバースランジ
1.足を一歩後ろに引いたらしゃがみます。この時前脚のくるぶしから踵のあたりに常に荷重しているようにしましょう。
2.後ろ足の膝が床に触れるぐらいで立ち上がります。
3.交互に繰り返します。
※バランスが取れない場合は無理せず他の種目を行いましょう。
鍛えられる筋肉:大殿筋、大腿四頭筋、内転筋、ハムストリングスなど
推奨ボリューム:片脚8~12回 2~3セット



バーベルが苦手な人向けの代用種目を紹介します。
ダンベルルーマニアンデッドリフト
1.足は腰幅、手は肩幅
2.お尻の位置を変えずに上半身をまっすぐ折り曲げる(膝は軽く曲がる)
3.もも裏にテンションがかかる感覚を得て元の位置に戻る
※バーベルが身体から離れていかないように
鍛えられる筋肉:ハムストリングス(もも裏)、大殿筋など
推奨ボリューム:8~15回 2~3セット
ゴブレットスクワット
1.足は肩幅、つま先やや外
2.くるぶしから踵のあたりに体重がかかりそのまま真下にしゃがみます
3.お尻で下のボタンをタッチするようにしゃがんで戻ります。
※重りを胸の前で持つことでお腹の力が入りやすくなります。
鍛えられる筋肉:大殿筋、大腿四頭筋、内転筋、など
推奨ボリューム:10~20回 2~3セット
リバースランジスライド
1.足を一歩後ろに引いたらしゃがみます。この時前脚のくるぶしから踵のあたりに常に荷重しているようにしましょう。
2.後ろ足の膝が床に触れるぐらいで立ち上がります。
3.上半身がやや前傾するとしゃがんだ時にお尻周囲にテンションがかかるのを感じれたら良いです。
※膝や腰に来てしまう方は無理しないようにしつつ、この動きができるように上の二つの種目が別の種目、ストレッチをやっていく必要があります。
鍛えられる筋肉:大殿筋、大腿四頭筋、内転筋、ハムストリングスなど
推奨ボリューム:片脚10~15回 2~3セット
以上フリーウエイトでの下半身のトレーニングでした。マシントレーニングはご紹介していないのは撮影上の都合もありますが、種目特性の違いが挙げられます。
というのは、地面(床)に足の裏がついているかいないか という問題です。
普段私たちが生活している環境は、地面や床に足裏が接地してその感覚を瞬時に捉えることで姿勢や動作を行います。マシンだけに頼ってしまうと姿勢や動作の制御という面では劣ります。ですのでより実践に近づけるためにもフリーウエイトをご紹介しました、もちろんマシンのメリットもたくさんありますので使い方次第です。
トレーニングの注意点
動作中に腰や膝に痛みや違和感を伴う場合は、他の種目に変えるか無理せずやらないようにしましょう。バーベルを担がない場合ではダンベルを使ったりして負荷を変えることもおススメです。
トレーニングが慣れてきたらプログラムを漸進させていく必要があります。回数だけでなく、セット数・インターバル・重量などを変化させていきましょう。こちらの記事を参考にしてください。


さらにパフォーマンスを上げたい人向け
姿勢・歩行・心肺機能・筋持久力・筋力・パワー・平衡性・柔軟性・協応性・(敏捷性・スピード)・メンタル・栄養
→心肺機能と栄養は見直しやすい要因になります。
個人的には歩行を変化させていくのは長時間の登山ではかなり大切ではないか。と考えていますが、これは実際のパーソナルトレーニングでないと難しい側面があるので、ブログでの取り上げはできません。
本気で登山に対して向き合っている人は、こちらにご連絡いただければパーソナルトレーニングもしくはメールで対応致します。
まとめ
登山がより疲れにくく良い身体の状態でできるように、トレーニングをご紹介しました。トレーニングを行う目的は、身体のキャパ を増やすこと。 効率の良い動き の獲得。 ジムへ足を運んだ際はケガのないようにお試しください。

